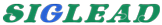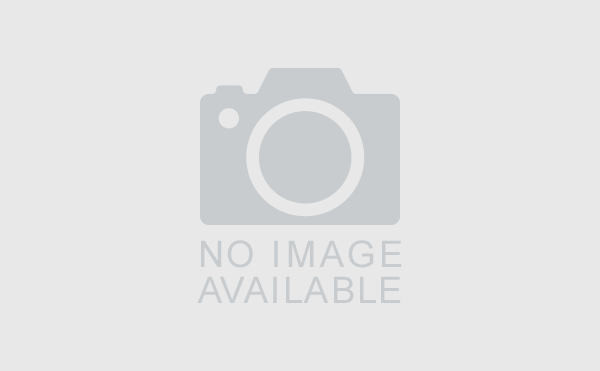SigNASⅡとSigNAS3の違い
今回は、SigNASⅡとSigNAS3の違いについて紹介します。
それぞれ下記弊社のホームページでも紹介されておりますのでご参照下さい。
尚、下記内容の詳細については直接弊社にお問い合わせ下さい。
両者の基本構成の外観写真を示します。
SigNASⅡ
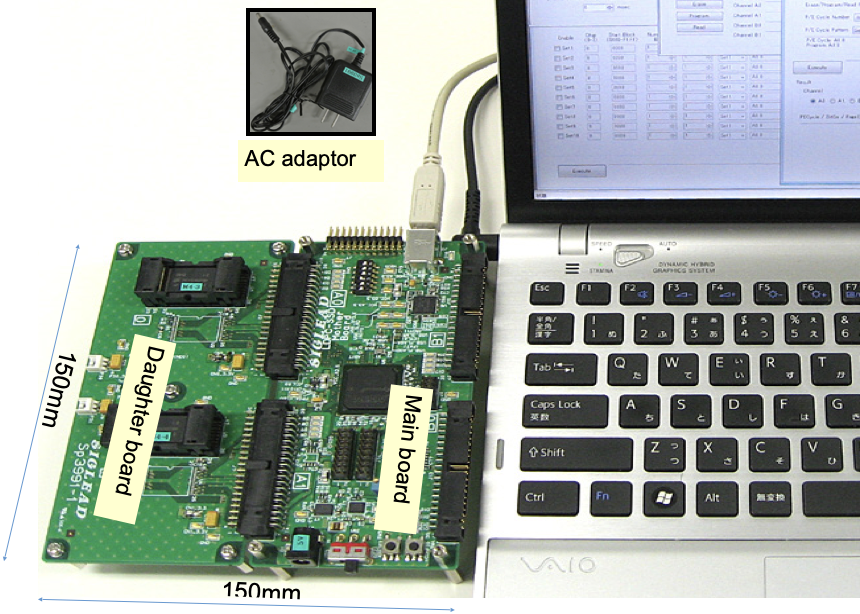
SigNAS3
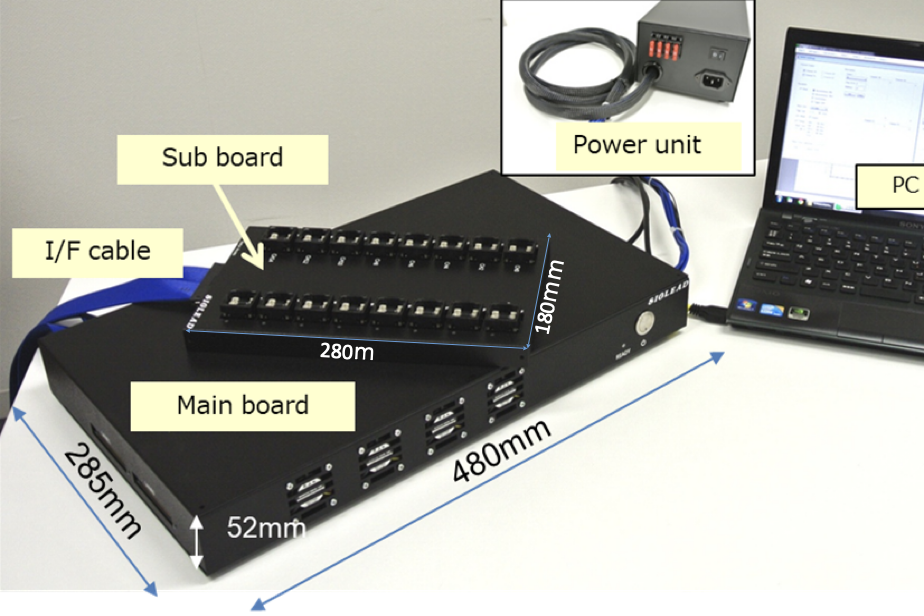
1. 基本構成
両者とも制御を司るメインボードと、測定対象のNAND Flash Memory (以下NAND)を載せるソケットを搭載したボード(SigNAS3ではサブボード、SIgNASⅡではドータ―ボード)で構成されます。
2. 外形
写真に記した寸法の通り、SigNASⅡはSigNAS3に比べてコンパクトです。
但し、SigNAS3は、メイン・サブボード間は標準長1mのI/Fケーブルで接続されているため、サブボードのみを実作業机上に置くレイアウトも可能です。
3. NAND最大搭載数
SigNASⅡ: 2個(TSOPのみ4個)、ドーターボード2枚接続構成時
SigNAS3 : 128個、サブボード8枚 x ソケット16個構成時
4. 制御PCとのI/F
SigNASⅡ: USB2.0
SigNAS3:USB2.0 or USB3.0
5. 操作性
両者ともにGUIベースで主な設定や操作が可能ですが、後発のSigNAS3の方がより多くの機能を備えています。
6. NANDの電圧設定、変更
SigNASⅡでは半固定で、ハードの変更が必要となります。
SigNAS3ではGUIまたはScriptでの設定、変更が可能でVccもVccqも0.5V刻みでの設定できます。
7. コマンドスクリプト
ユーザー独自の測定シーケンスを記述するスクリプトに使用するコマンドについて、SigNASⅡは基本的なコマンドが1文字ですが、SigNAS3は6文字のため機能との関連性が分かり易いと思われます。
例
| 機能 | SigNASⅡ | SigNAS3 |
| Block Erase | e | BKERAS |
| Page Program | p | PGPROG |
| Page read & dump | g | PGRDDM |
| Page read & compare | c | PGRDCP |
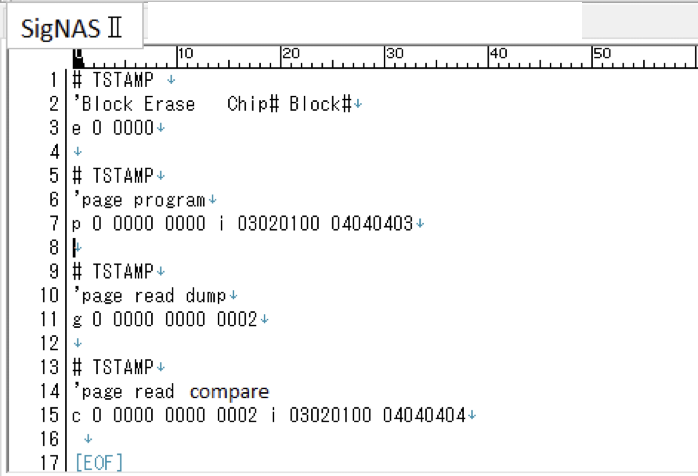
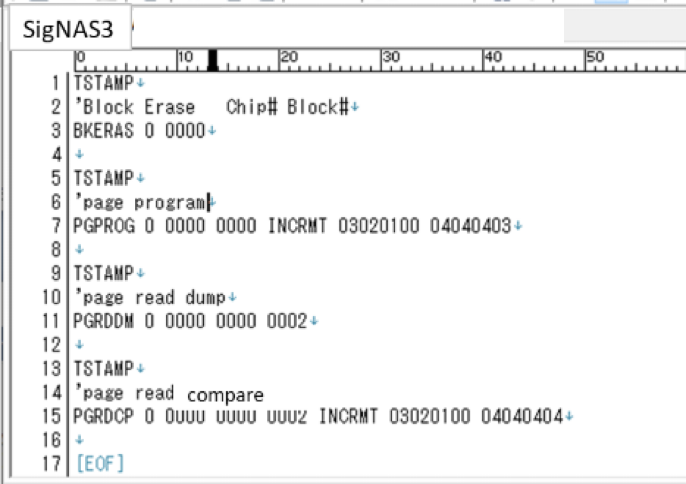
8. 機能
両者に基本機能の差はありません。
しかし、SigNASⅡはハード的なリソースが SigNAS3に比べ限られているため、新機種NANDや新機能の対応に時間がかかったり、対応困難(Vth分布:https://siglead.com/vth-distribution-measurement/ など)な場合がございます。
9. 価格
基本構成の比較では、大きな差はありません。
10. その他
SigNASⅡは、本体に冷却ファンが(不要のため)装着されておらず、静かです。
以上、SigNAS3は、機能、性能共にSigNASⅡより優位性があり、研究評価にも量産試験にも有用なテスターです。